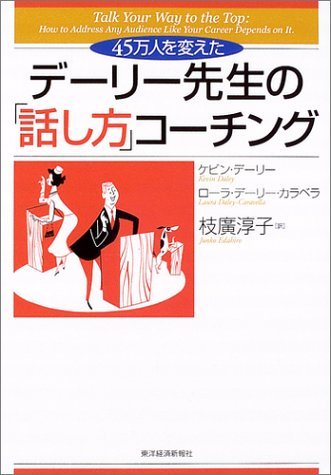エダヒロの本棚
上司に対してプレゼンテーションするとき、悪い知らせを伝えなくてはならないとき、司会を頼まれたとき、人々をやる気にさせたいとき......、ビジネスやふだんの生活で遭遇する16の場面を取りあげ、「何を期待されているのか」「何が必要か」「どのように話せばよいか」、今日からすぐに使えるヒントや注意点が盛りだくさんの具体的な指南書です。「話し方」だけではなく、「考え方」「対応の仕方」にも大いに役立ちます。
訳者まえがき
一〇年ほどまえから通訳の仕事をしている私は、これまで何千ものスピーチやプレゼンテーションを、日本語から英語へ、英語から日本語へ、通訳してきた。国際会議でのスピーチやプレゼンだけでなく、外国と日本の企業が合弁事業を立ち上げるための商談、日本にも支社のある多国籍企業のグローバル会議など、場面や目的、話し手や聴衆はさまざまであるが、「人前で話をする」人々の言語面でのサポートをしてきた。
条約を決めるための国際会議で、各国のいろいろな思惑や駆け引きが錯綜するなかで物事が決まっていくようすを、ブースから同時通訳しながら感心して見ていたこともある。企業の社内会議で、偉い方が自分の偉さを印象づけようとスピーチをされたのだが、まったく逆効果の波紋が聴衆に広がっていくようすを、舞台脇の通訳席から見ていたこともある。商談通訳では、もともとは「いっしょにビジネスをやろう」という同じ思いで始まったはずの会合が、どういうわけか、誤解と疑念の連鎖にはまりこみ、喧嘩別れで合弁の話も立ち消え、という場面もあった(喧嘩の通訳は大変だった! もっとも、通訳料は払ってもらえたのでほっとしたが)。
通訳は「伝える」ためのお手伝いだ。「伝わってナンボ」の職業だと思っている。しかし、いろいろな人の通訳をしているうちに、そもそもの話し手のレベル以上には通訳できないんだよなあ、と思うようになった(当然である)。話し手こそ「伝える」ために(多くの場合、伝えることで人を動かすために)、話をしているはずなのだが、そのスタンスやレベルには大きな幅があるのだ。
「同じように人前で話しても、通じる人もいれば、通じない人もいる。何が違うのか?」――通訳者として数多くのスピーチやプレゼンを聞いてきた経験から、数年前に私は「優れたコミュニケーターに共通する三原則」を発見した。
その1 伝えるべき内容を持っている
その2 伝えようという気持ちを持っている
その3 伝えるためのスキルを持っている
これらすべて満たしてはじめて良いコミュニケーターになれる。
人前で話をする人なのだから伝えるべき「内容」があるのは当然だ、と思うかもしれないが、実際にはそうでもない場合もある。「その場で話をすること」自体に意味である、という人や場面も稀にあるのだ。
また、「内容」は持っていても、伝えよう、伝えたいという「気持ち」がないまま、話す人もいる。ただ発表することが目的であり、その結果、伝わっても伝わらなくても自分には関係ない、というタイプ。これでは「発表実績」にはなっても、人を動かすことはできない。
そして、いちばんもったいないなあ、と思うのは、「内容」も「気持ち」もありながら、伝えるための「スキル」に欠けているためにうまくいかない人だ。伝えたい! という気持ちは伝わってくるものの、話の仕方が支離滅裂だったり、論理が見えにくかったり、要するに「聞く側」に添った話し方ができないのである。
本書はまさに、その「スキル」を身につけるための絶好の書である。「この本に盛り込まれたアドバイスやヒント、すぐに使えるフォーマットがあれば、あの場面だって、あの人だって、あの人間関係だって、救われただろうに!」と、具体的な場面が次から次へと思い浮かぶ。
そして何より、企業や政府のトップに本書を読んでほしい。不祥事が起こるたびに、記者会見が開かれる。世間の耳目が「トップは何と言うか、どう言うか」に集まっている。それなのに、うつむいたまま原稿を棒読みするだけ、というトップが多い。
これでは、「本当に申し訳ないと思っているのか」「口先だけではないか」と思われても仕方がない。これからどうするつもりか、の話も説得力を持たず、言い訳か言い抜けに聞こえてしまう。
しかし、そういううれしくない場面ですら、状況を最善の方向へ好転させる「話し方」があるのである。たとえば本書の11章を見てほしい。何をどう話すべきか、どう準備をし、何に気をつければいいか、具体的に書いてある。このようなスキルを身につけずして「リーダー」とは言えないだろう。
本書は、主に企業や組織で直面する一六の場面を取りあげ、詳しく「考え方、話し方」を掘り下げ、今日からすぐに使えるシンプルなフォーマットやヒント、注意点をたっぷり盛り込んだものである。
確かに、場面によって必要なスキルもさまざまだ。しかし、どういう場面でも、根本的に重要なポイントが一つある。「いまここで伝えるその目的は何か?」を十分に意識することである。目的が明確になれば、「何を」「どのように」は自ずと決まってくる。
「上司に異論を唱えるとき注意すること」の章は、ビジネス場面に限らず、夫婦や友人などあらゆる人間関係にこれ以上ないほど有効な指針を与えてくれる私のお気に入りの章だが、この章を読むと、この「まず目的ありき」がよくわかる。
上司と意見が違うという場面はよくあるだろう。「なんだってそんな馬鹿なことを!」「まったくわかっていないんだから」とイライラする経験は多くの人がしているはずだ。では、その場の自分の「目的」は何か? 多くの人は無意識のうちに、「むっ」とした自分の思いを沈めることを目的とする。すると「やっつけたい」「スカッとしたい」という闘争心が出てくる。その結果、「違いますよ!」「それじゃ、うまくいきませんよ!」という、言い争いへ一直線の一言となってしまう。両者ともに嫌な気持ちになり、後味が悪いだけならまだいいが、その後の人間関係にもひびが入ってしまうこともある。
上司の意見が間違っていると思ったとき、自分の「本当の目的」が、「その場でスカッとしたい」という極めて短期的な目的ではなく、「上司と険悪にならず、しかも自分が正しいと思うことを実行する」ということだったら? その目的をしっかり意識して、第13章に書いてあることを実行すれば、目的にかなう対応ができるはずだ。上司も自分も嫌な気持ちになることなく、しかも自分の正しいと思うことが実行でき、会社も喜ぶだろう。
本書には一六の場面が載っているが、本書全体から学べること、そして、この一六以外の場面にも応用できることのひとつは、このように「目的を意識する」であると思う。これはビジネス以外の状況でも、同じように有効である。
本書は、どう繕うか、どう飾るか、というコスメティックな「話し方」の本ではない。さまざまな状況で、何をどう考えたらよいのかを示すことで、どのような状況でも自分で考えられるように指南を与え、そのうえで「どう話したら、目的に最も資するか」まで教えてくれる。骨太でありながら、著者の軽妙な話術が楽しくあっという間に読める本だ。
「いつか、この著者のスピーチの通訳をしてみたい!」……人生の楽しみがまた一つ増えた。
二〇〇四年秋
枝廣淳子
---------------------------------------------------------------------------------
訳者あとがき
私の「伝えること」へのこだわり(?)は、大学時代にさかのぼる。臨床心理学でカウンセリングを勉強していたので、「相手の言いたいことを自分は本当にわかっているのか?」「自分の伝えたいことが伝えたいように伝わっているか?」と、自分の腑(自分及び他人とのやりとりに関する感覚器)を鍛える毎日だった。通訳の仕事もまさに「伝える」ことの勉強の場である。話し手から(時には反面教師として)学ぶとともに、「自分の通訳は伝わっているか?」を突きつけられるスリリングな仕事なのだ。
また、環境ジャーナリストという名刺も持っているので、講演やパネルディスカション、セミナーなど、自分でも人前で話をすることがよくある(私の発言を同僚の通訳者が通訳してくれたりする!)。英語や自分マネジメントの教室も開催しているので、十数人の受講生に伝えたり教えたりする場面もある。五年ほどまえから、環境メールニュースを出しているが、これも「書き言葉でどう伝えるか」を毎日実験しているようなものである。
私の活動は外から見ると、通訳や翻訳、執筆や講演など多岐にわたるように見えるらしいが、やっていることはすべて同じで「伝えること」と「つなげること」だと思っている。その私にとって、本書の翻訳は、「どういう話し方をすればいいか?」(中身)と、「そのコツやポイントをどう伝えようとしているか?」(論の進め方)と、「その本をどう訳したらいちばん伝わるか?」(翻訳)の三つのレベルで同時に勉強になった。「一粒で三回おいしい」「三重喜」の翻訳ができて、とてもうれしく思っている。
私の師事するアースポリシー研究所のレスター・ブラウン所長は、書き言葉も話し言葉も、非常に説得力があってわかりやすく、コミュニケーターとして高い評価を得ている。ちなみに、ワールドウォッチ研究所時代から、研究員の志願者にコミュニケーション能力の厳しいテストを課していたと聞く(このためか未だに日本人の研究者は誕生していない)。
レスターは、「ニュースリリースでも記者発表でも、読み手や聞き手がどう受け取っているか、自分の伝えたかったメッセージはその通り伝わっているか、つぶさにチェックして次回のプレゼンテーションの仕方に反映している」と話してくれたことがある。ワールドウォッチ研究所を設立する前は、米国農務省に勤務していたが、農務省には各部署ごとに、外部からのコメントなどをファイルにまとめて置いてある部屋があったそうだ。彼は、そこにこっそりしのびこんで(?)自分へのコメントはもちろん、評価の高い人はどうして高いのか、低い人はどこがいけないのか、かなり研究したよ、と教えてくれたことがある。
「わかってもらうために、インパクトを与えるために、リリースを書き、発表をしているのだから、ちゃんとわかってもらえているのか、インパクトが与えられているかは、いつも気をつけている」とレスター。「でも、」と続けて、「イデオロギーの違いや主張の違いから来る批判や非難、苦情には、一言たりとも耳を貸さないけどね」。
こんなレスターとのつきあいに刺激を受け、自分でも人前で話したり、大事なことを伝えようとしてきた経験から、「伝えること」で大事だと思っていることが二つある。
ひとつは、「人によって、受け取りやすいメッセージのスタイルが違うので、手を替え品を替えして伝えること。たくさんの人が対象なら、いろいろなスタイルを盛り込むこと」だ。自分の得意なスタイルに固執していると、そのスタイルを得意とする相手にしか届かないからである。
もうひとつは、「伝えっぱなし」(正確には伝えたつもりっぱなし?)ではなく、「こういう目的・聴衆だから、こう伝えよう」と計画し(P=Plan)、伝えてみて(D=Do)、その結果「本当に伝わったか?」をチェックし(C=Check)、「では次回はこう伝えてみよう」と改善をはかる(A=Action)、という「コミュニケーションのマネジメントシステム(P→D→C→A)」を回すことで、自分の伝え方そのものを改善していくことだ(このために私は、講演では必ずフィードバックをもらうためのアンケートをお願いしている)。
「生まれつき話が上手」「何の苦労もなく、誰にでも何でも伝えられる」という人はいない。もちろん、持って生まれた資質はあるにしろ、いまやすばらしいスピーチやプレゼンテーションをする人も、自由自在に人々をつないでいくようにみえるコミュニケーターも、経験のなかで学びながら上達してきたはずだ。本書をその向上のための手引きとすることで、対応できる幅も深さも広がり、コミュニケーションの質の高さもぐん!と高まることは間違いない。
東洋経済新報社・出版局の井坂康志氏、中村実氏にはお声掛けをいただき、いろいろとお世話になった。下訳は私の主宰する実践和訳チームから、五頭美知氏をまとめ役に、伊藤智子、小野寺春香、小林紀子、小宗睦美、庄司晶子、角田一恵、豊高明枝、中小路佳代子、西垣亜紀、藤津ふみえ、山田はるみ、横内若香、渡辺千鶴の各氏が担当し、アシスタントの関美穂氏にも大いに助けてもらった。翻訳者も「翻訳しながら話し方や考え方の勉強にもなる!」と大喜びだった本書が、みなさんのお役に立つことを願っている。