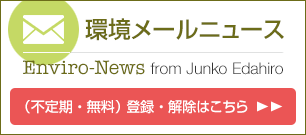エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
永続地帯 (2025年8月25日掲載)
先日、千葉大学倉坂研究室と環境エネルギー政策研究所が「永続地帯2024年度版報告書」を公表しました。「永続地帯」とは、その区域で得られる再生可能エネルギーと食料によって、その区域におけるエネルギー需要と食料需要の全てを賄うことができる区域のこと。エネルギーと食料を自給できれば、いざというときにも強いし、温暖化対策にもなるし、素晴らしいですよね。
日本にはそういう市町村がいくつぐらいあると思いますか。この調査は20年近く前から行われていますが、「永続地帯」は少しずつ増えてきていて、2023年度は134でした。もっともっと増えてほしいですね。
ここでは、特にエネルギーの自給について紹介しましょう。日本全体の23年度の再生可能エネルギーの導入動向をみると、風力発電の伸び率が太陽光発電を上回っています。再エネ供給量は前年度比で8%近く増えており、11年度比では約4.5倍に増加しています。
「その都道府県の民生・農林水産業用のエネルギー需要のうち、どのくらいを再エネで満たしているか」のトップは、秋田県で、54.3%でした。続いて大分県、福島県、群馬県、三重県です。この5県は50%を超えています。素晴らしいですね。 みなさんの都道府県は頑張っていますか。
「永続地帯」はエネルギーと食料の両方の自給を見ますが、エネルギーだけに注目する場合は「域内の民生・農林水産用エネルギー需要を域内で生み出された再エネで自給できる市町村」を「エネルギー永続地帯」としています。その数は23年度に234と、11年度の4.7倍に増加しています。それぞれの市町村が、工業用はともかく、民生・農林水産用エネルギーを自分たちで賄えるようになれば、レジリエンスの高い地域になります。これを日本全体で見ると、民生・農林水産用エネルギー需要のうち、再エネで満たしている割合は、11年度の3.8%から23年度は20.9%に増加しています。でも、もっと加速したいですね。
都道府県や市町村は、ふるさと納税額で競うより「うちの自治体もやっと永続地帯になったよ」とか「地域的エネルギー自給率」を競ってほしいです。こういった自給率が、ふるさと納税額に連動するしくみになれば、もっと良いと思います。