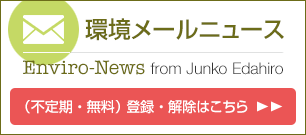エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
ブルーカーボンの認知度は?
あっというまに7月ですね...。
6月15日に2025大阪・関西万博「BLUE OCAEN DOME(ZERI JAPAN)」のパビリオン催事でさせてもらった講演のようす、こちらにアップされています。45分間、よろしければご覧下さい。
ブルーカーボン&豊かな海を守るには
https://www.youtube.com/watch?v=-zKjXxrdsTU&t=221s
ブルーカーボンに関わる活動をしていると、「以前に比べると、ずいぶん認知度や理解度も上がってきたなあ」と思うこともあるのですが、私たち幸せ研で調査したところ、現実は「まだまだ...」という結果でした。。。
図表はウェブからご覧下さい。
~~~~~~~~~~ここから引用~~~~~~~~~~~
ブルーカーボン、9割が「意味を知らない」と回答
持続可能な社会に向けた意識調査を実施
2025年3月、幸せ経済社会研究所(事務局:有限会社イーズ)は、「持続可能な社会に向けた意識調査」をオンラインで実施しました。
本調査は、環境・経済・倫理など、持続可能な社会に関わる多様な課題についての認知度や関心を把握することを目的としています。
調査項目のひとつとして、「ブルーカーボン」「グリーンカーボン」「バイオ炭」に関する認知度を尋ねました。
【用語解説】
・ブルーカーボン:海藻や海草などの海洋生態系によって吸収・固定される炭素
・グリーンカーボン:森林など陸上の植物によって吸収・固定される炭素
・バイオ炭:木材・竹などバイオマスから作った炭で、炭素を長期間固定できる
その結果以下のような結果が得られました(図表1)。
「ブルーカーボン」については、「知らない」と回答した人が74.2%、「聞いたことはあるが、意味は知らない」が16.7%と、合計90.9%がその意味を理解していないことが明らかになりました。
同様に、「グリーンカーボン」では84.3%、「バイオ炭」では87.0%が「知らない」または「意味は知らない」と回答し、いずれも認知度が非常に低いことが浮き彫りとなりました。
また、「説明することができる」「意味を知っている」「大まかな意味を知っている」と回答した人に対し、それぞれが温暖化対策として有効かどうかを尋ねたところ、いずれの項目も約65%が「有効」と回答しました(図表2)。
この結果から、ブルーカーボンなどの概念は十分に知られていない一方、認知している人の多くはその重要性を理解していることが示されました。今後、持続可能な社会の実現に向けて、こうした概念の普及と啓発を通して、実際の取り組みを推進していくことが求められます。
【本調査について】
調査名:「持続可能な社会に向けた意識調査」
実施日:2025年3月26日〜27日
調査方法:インターネット調査
有効回答数:1099人
回答者属性:全国の20〜69歳の男女
使用システム:Questant
本調査では、年代・性別・地域(大都市/中小都市・地方)の比率が、日本の人口構成に近づくよう調整しています。
※本リリースのPDFはこちらからご覧ください
<本件に関するお問い合わせ>
幸せ経済社会研究所(事務局:有限会社イーズ)
TEL:0557-48-7898
Mail:info(@)es-inc.jp
※(@)を@に変えてお送りください。
~~~~~~~~~~~引用ここまで~~~~~~~~~~~
もっともっと頑張らねば!ですね~。
さて、最後に読書会のご案内です。
7月の幸せ研読書会では、地域や組織で「お客様」が増えてしまっている現状をどう変えていったらよいのか、ヒントがぎっしり詰まった1冊を取り上げます。ぜひ一緒に考えてみませんか。
7月15日(火)開催
『あそびの生まれる時 「お客様」時代の地域活動コーディネーション』を読む
7月は、西川正氏の書籍、『あそびの生まれる時 「お客様」時代の地域活動コーディネーション』を、課題書に取り上げます。
冒頭の章から少し引用します。地域でも職場でも、心当たりがある方、なんだかやりにくいんだよねえと思っている方、いらっしゃるのでは?
~~~~~~~
システム化=市場経済によるサ--ピスが生活のすみずみまで行き渡るにつれて、地域の活動も、誰かが誰かにサービスをする、というスタイルが広がってきている。
たとえば、PTA などで、その年役員になった人が、役員ではない会員にヤキイモをふるまうという形式をよく目にする。しかし、これをしていると役員以外の人、とくに前に役員をやったことがある人などは、「遅い」「小さい」「まずい」「高い」など消費者目線か、厳しい先輩の「チェック」目線になりがちだ。
「私たちの時はこうだった」「今年はこれがない」「よそではこんなことをしているらしい、うちではやらないのか」と。現役役員さんたちは、こうした評価の目線をおそれて、落ち度がないようにと緊張する。
そして、そんな1年間を過ごすと、「もうこりごり。地域の活動にはかかわりたくない」ということになる。そして、「私たちの代は、がまんしてやったのに」と、次年度の役員に厳しい目線を送るようになる。
~~~~~~~
そんな中で、どうやって「てんやわんや」「あーだこーだ」「わいわい」という、あらかじめ決められているのではない、その場ならではの交流や出会い、盛り上がりをつくり出し、みんなで楽しみ、みんなでワガコト化していくことができるのでしょうか。
「どんな時に人は、「あたま」ではなく、「こころ」そして「からだ」が動くのか?」――著者は、路上で、オンラインで、さまざまな場づくりをする中で実感してきたポイントを2つ、詳しくコツも含めて、教えてくれます。
本書に盛り込まれた多くの具体例や、それらから得られたノウハウなどは、地域
活動のみならず、組織内外でのコミュニティを形成しようとしている方々にも多
くの学びとヒントがあります。そして、日本の教育のあり方も、深く考えさせられる(そして、少なくとも自分の家庭や地域では変えていける!)点もたくさん!
本当に大事なこと、ゆっくりじっくり考えてみませんか。変えていきませんか。みなさんのご参加をお待ちしております。
■日時:2025年7月15日(火)18:30 ~20:30(開場18:15)
■会場:オンライン (ZOOM使用予定)
(お申込みいただいた方にアクセス用のURLをご案内いたします)
■課題書:『あそびの生まれる時 「お客様」時代の地域活動コーディネーション』
(著:西川正)
https://www.ishes.org/links/2025/bks_id003654.html
■参加費:2,200円(税込)
■詳細・お申込みはこちら