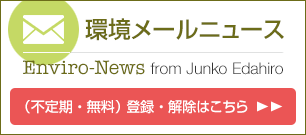エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
2013年04月27日
『日本の気候変動とその影響』2012年度版 (2013.04.27)
温暖化
昨日に続き、温暖化に関するわかりやすい最新レポートをご紹介します。
気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気候変動とその影響』(2012 年度版)
http://www.jma.go.jp/jma/press/1304/12a/report_full.pdf
(以下、プレスリリースより)
4月12日に、文部科学省、気象庁、環境省は、日本を対象とした気候変動の観測・予測・影響評価に関する知見を取りまとめたレポート「日本の気候変動とその影響(2012年度版)」を作成し、レポートの概要をまとめたパンフレットと合わせて公表しました。
このレポートは、さまざまな自然システムが気候変動による影響を受けつつある中で、国や地方の行政機関、国民が気候変動への対策を考える際に役立つ 最新の科学的知見を提供することを目的として、主に日本を対象とした気候変動の観測・予測及び影響評価分野の最新の知見を統合・要約し、取りまとめたものです。
今回のレポートでは、観測結果に基づく気候変動の現状と将来の予測結果について、前回の統合レポート(平成21年10月)公表後に得られた 最新の知見を盛り込むとともに、気候変動により現在生じている影響及び将来予測される影響についての記述を大幅に拡充し、 特に気候変動への適応策を考える際に役立つ資料としています。
また、気候変動に関してよく抱かれる疑問について、コラムを活用してわかりやすく解説したほか、レポートの概要をまとめたパンフレットも合わせて公表しました。
レポート作成にあたっては、住明正 国立環境研究所理事長を委員長とする専門家委員会を設置し、レポートの構成等の検討や査読等を実施しました。
気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート『日本の気候変動とその影響』(2012 年度版)
http://www.jma.go.jp/jma/press/1304/12a/report_full.pdf
第1章 気候変動のメカニズム 第2章 気候変動の観測結果と将来予測第3章 気候変動による影響第4章 将来の気候変動に対する適応策の現状と課題
第1章の気候変動のメカニズム、とてもわかりやすく書かれているので、多くの方にとっては"おさらい"になると思いますが、ご紹介したいと思います(メールでの読みやすさのため、pdfレポートにはない改行を入れています)
一緒に載っているグラフや図がとてもわかりやすいので、ぜひ上記のpdfもご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~ここから引用~~~~~~~~~~~~~~~~~
第 1 章 気候変動のメカニズム
この章では、気候変動対策を考えるにあたって必要となる基本的な用語や概念、及び近年の気候変動の要因について解説する。
1.1 気候変動とその要因
1.1.1 気候とは
気候とは、一般に「十分に長い時間について平均した大気の状態」のことをいう。平均によって短期間の変動が取り除かれるため、それぞれの場所で現れやすい気象の状態と考えることができる。具体的には、ある期間における気温や降水量などの平均値や変動の幅によって表される(コラム1 参照)。
平均期間より長い時間で見ると、気候は必ずしも定常的なものではなく、様々な変動や変化をしている。このような変動や変化を広く「気候変動」と呼ぶ。本レポートでは、基本的に人為的要因によると推定される長期的な変動や変化を対象として「気候変動」の語を用いるが、自然変動を含む気候の変化や変動を「気候変動」と記述しているところもある(詳しくはコラム 5 参照)。
1.1.2 気候を決める要因と気候システム
気候は大気の平均的な状態を示すものであるが、大気や水の循環には海洋、陸面、雪氷が深くかかわっている。このため、大気と海洋・陸面・雪氷を相互に関連する一つのシステムとして捉えて「気候システム」と呼ぶ。
地球規模の気候は、気候システムに外部から強制力が加わることで変化する。外部強制力には自然的要因によるものと人為的要因によるものがある。自然的要因としては、太陽活動の変動や、火山噴火による大気中の微粒子「エアロゾル」の増加などがあり、人為的要因としては、人間活動に伴う化石燃料の燃焼や土地利用の変化などによる温室効果ガスの増加やエアロゾルの増加などが挙げられる(表1.1.1)。
一方、気候は外部強制力を受けなくとも気候システム内部の要因によっても変動する(内部的な自然変動)。内部の要因とは、大気・海洋・陸面が自然法則に従って相互作用することであり、これによる自然変動の代表的な例にはエルニーニョ/ラニーニャ現象がある。
地球全体の平均気温は、地球に入ってくるエネルギー(太陽放射)と地球から出ていくエネルギー(外向きの長波放射)のバランスによって決まっている。人為的要因が大きくなると、図 1.1.1 のように地球規模でのエネルギーのバランスに変化をもたらし、気候に大きな影響を与えることになる。
放射強制力は、気候に与える影響力を定量的に評価し比較するための物差しとなるもので、地球のエネルギー収支のバランスを変化させる様々な人為起源及び自然起源の要因の影響力を示す。正の放射強制力は地表を加熱し、負の放射強制力は冷却する。
産業革命以前(1750 年頃)を基準とした 2005年時点の放射強制力の内訳をみると(図 1.1.2)、正の放射強制力については、長寿命の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類)及び対流圏オゾンの増加による温室効果の寄与が大きい。
一方、負の放射強制力は、主に人為起源のエアロゾル(硫酸塩など)によってもたらされている。エアロゾルは、直接太陽放射を散乱・吸収して日射を減衰させる(日傘効果)。また、雲の凝結核となることから雲粒径や雲量の変化を通じて間接的に雲アルベド(反射率)を増加させ、地表に届く日射を減少させる。
1.2 温室効果ガス濃度の変化
温室効果ガス濃度は、20 世紀後半以降、世界各地でモニタリングされるようになった。日本でも、気象庁が綾里(岩手県)、南鳥島(東京都)、与那国島(沖縄県)において、国立環境研究所が落石岬(北海道)、波照間島(沖縄県)において、それぞれ二酸化炭素などの温室効果ガス及び他の微量ガスの観測を継続的に行っている。
大気中の二酸化炭素濃度は、北半球の春から夏に減少し、秋から翌春に増加する季節変動を伴いながら、年々明瞭に増加している(図 1.2.1)。季節変動は主に陸域生態系の活動(植物の光合成や土壌有機物の分解)によるもので、南半球は北半球に比べて陸地が少なく森林等の植物も少ないため、季節変動が小さい。
世界気象機関(WMO、以下「WMO」という)の温室効果ガス世界資料センター(WDCGG、以下「WDCGG」という)の解析によると、二酸化炭素の世界平均濃度は、2011 年時点で 390.9ppm8と産業革命以降 40%増加した(表 1.2.1)。
また、最近 10 年は年平均 2.0ppm の割合で増えており、増加率は 1990 年代(年平均 1.5ppm)よりも大きくなっている。二酸化炭素以外の温室効果ガス濃度も増加しており、特にメタンの2011 年の平均濃度は 1,813ppbと産業革命以降154%の増加となっている(表 1.2.1)。
図 1.2.2 は、氷床コアから得られた過去 80 万年における二酸化炭素濃度と気温の変化である。これまで、およそ 10 万年毎に氷期と間氷期が繰り返され、寒冷な氷期に比べて温暖な間氷期には、二酸化炭素濃度が高かったこと、氷期の最寒冷期と間氷期の間で約 100ppm の濃度差があったことがわかる。
これらは、地球の公転軌道や自転軸の傾きの周期的な変動に起因する気候の変動をきっかけとして二酸化炭素などの温室効果ガス濃度が変化し、さらに気候の変動を促進した結果と考えられている。近年の二酸化炭素濃度(図1.2.1)は、過去 80 万年のいずれの間氷期における濃度(~300ppm)よりも遙かに高く、過去 80万年にわたる地球大気の歴史の中でも極めて特殊であることがわかる。
1.3 近年の地球温暖化の原因
19 世紀後半以降、世界の平均気温や海面水位は、長期的に上昇している(図 1.3.1)。また、海洋表層の貯熱量は、1950 年以降上昇と下降を繰り返しつつ増加しており、水温の上昇が海面のみならず海洋内部まで及んでいることを示している。これらの観測結果により、気候システムが温暖化していることには疑う余地がないとされている(IPCC, 2007a)。
観測された地球温暖化が自然変動によるものなのか、人為的要因によるものなのかは、気候モデルで強制力を分離して計算した結果から推測できる。図 1.3.2 は世界の平均地上気温の変化について観測値とモデルによる再現シミュレーションを比較したものである。自然起源と人為起源の強制力の双方を考慮した気候モデルの計算結果(赤陰影)は、観測された気温の変化(黒線)、特に 20 世紀後半の気温上昇をよく再現している。
一方、人為起源の強制力を考慮していない計算結果(青陰影)では、この気温上昇は再現されていない。この違いは陸域に限らず、海洋においても同じである(図 1.3.2 (b), (c))。
以上に紹介した観測結果及び気候モデルによる 20 世紀気候再現実験の結果等に基づき、IPCC(2007a)は、「20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い。」とした。
~~~~~~~~~~~~~~~~引用ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~~
近年、世界平均気温の上昇が停滞していることから、「地球温暖化は止まったのではないか」という人もいますが、これについては、コラム 4 「地球温暖化は止まった」のではないか、をどうぞ!
また、この第1章につづく第2~4章もお薦めです。昨日の気象庁のレポートで紹介した気温や降雨等の影響だけではなく、海面水位、水環境・水資源、水災害・沿岸、自然生態系、食料、健康への影響についても、グラフや地図等を使ってわかりやすく説明されています。適応策についても、海外の取り組みや日本の先進自治体の取り組みの紹介もあります。また各所にあるコラムも、温暖化についてのいろいろな疑問に答えてくれます。
IPCCの最新レポートは2007年に出されたものですが、現在、第5次評価報告書の準備が進められています。一連のレポートのうち、最初のものは今年の秋に出される予定です。
IPCC 第 5 次評価報告書 第 1~3 作業部会報告書 目次(仮訳) はこちら。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14497&hou_id=11735
これをみると、第4次評価報告書に比べて、影響や適応に関する第2作業部会の報告書が2部構成となり、分量的にも大きく増えていることがわかります。
「温暖化は本当か、どのくらい温暖化するのか」ということから、「温暖化によってどのような影響が(地球に、地域的に)出てくるのか」「それに対して、どのように適応策をとっていく必要があるのか」ということに、力点がシフトしているということです。この事実自体を重く受けとめなくてはならないですね......。