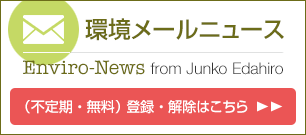エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
科学者有志による意見書「IPCC報告の科学的知見について」 (2010.10.16)
IPCCの信憑性について「クライメート・ゲート」などと騒がれましたが、[No.1822] で「クライメート・ゲート事件の顛末は?」としてお伝えしたように、独立調査委員会が「結論としては、データねつ造などの科学的な不正は見つからなかったこと、IPCCの結論になんら影響を及ぼさない」ことをあらためて確認する報告書を出しました。
http://daily-ondanka.com/faq/archives/id002724.html
9月の終わりに、IPCCの報告書に関わった日本の科学者・研究者たちが、「IPCC報告の科学的知見について」という意見書を発表しました。
IPCCの信憑性についてのみならず、私たちの「科学とのつきあい方」を考える上でも重要なメッセージだと思いますので、ご紹介します。
(注:メールでの読みやすさのため、原文にない改行を入れています)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
IPCC報告の科学的知見について
1. 本文の目的
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、1988年11月発足以来4度にわたって気候変動に関する厖大な報告を発表してきた。気候変動問題に関連した科学者達によって執筆されたこれらの報告は、その時点でもっとも信頼できるこの分野の科学的知見の集大成であり、さまざまな機会に引用され、特に気候変動に関する枠組条約会議やサミットなど気候変動への対応政策を論議する場でしばしば取り上げられてきた。
だが、IPCC報告の内容や性格がそうした外部の人々に十分正しく理解されているとはいいきれない状況が見られる。IPCC報告が特に以下に述べる2つの点で不当に信頼性を疑われたり(下記2.)、逆に政治的決定に濫用されている(下記3.)ように思われる。
今春以来、この問題に関心の強い関係科学者有志が集まり議論した結果、この2点についての有志の見方を世間に公開することとした。これによって、社会の人々が、従来の、そして今後のIPCC報告の意図する内容を正しく理解されることを強く期待する。
注:関係科学者有志の氏名(五十音順) 石谷 久、江守正多、沖 大幹、茅 陽一、鬼頭昭雄、杉山大志、住 明正、 関 成孝、松野太郎、山口光恒 2. 報告書内容の信頼性について
本文で取り上げる第一のポイントは報告書に盛られた科学的知見の信頼性である。報告書に盛り込まれた内容がどこまで信頼できるかは、報告書を読む人にとって当然第一の関心事である。しかし、2009年末頃から、IPCCの報告書の内容をめぐっていくつかの出来事があった。これを大きくわけると次の2つになる。
1) データの操作に関するもの2001年の第3次報告書で、温暖化の事実を如実に示すとされる図の作成過程で、恣意的操作が行われたことを示唆するとされるe-mailが明るみに出された。(いわゆる「クライメート・ゲート」疑惑)
2) 記述の信憑性に関するもの2007年発表の第4次報告書第2作業部会報告「気候変化の影響評価・適応策・脆弱性」の中で、「ヒマラヤの氷河が2035年までに消失する可能性が高い」という重大な記述がなされているが、これがIPCCの引用基準を満たさない科学的根拠に欠ける記述であることが指摘され、それに対してIPCCもこの記述を誤りと認めた。また、これ以外にも、報告書の中の小さなミスや引用の不適切、バランスの不適切などの指摘がなされている。
これらに対してどのような対応が行われたであろうか。
1)に関しては、問題の生じた英国において、下院の科学技術委が設けた特別委や関係大学の委託した2つの委員会が真相究明を行い、オリジナルデータの公開等については問題があるものの、科学的内容については問題がないとの結論を得た。2)に関しては、一般的にIPCC報告の信頼性や透明性を更に高める目的で、IPCCが第三者(IAC:インター・アカデミー・カウンシル)に報告書作成過程や組織の運営体制に関するレビューを依頼し、その報告が8月末に発表されたところである。
ただ、いずれにせよこれまで指摘された誤りは殆どが軽微なものであり、これによってIPCCがこれまでまとめた科学的知見の主要なものが揺るぐわけではない。
第4次報告で指摘された主要な2つのポイント、すなわち
*地球温暖化が起きていることは疑う余地がない
*20世紀後半以降に生じた温度上昇の大部分が、人為起源温室効果ガスの増加によるものである可能性が非常に高い
の妥当性については、世界の多くの科学団体・国際研究プログラム(ICSU:国際科学会議、WCRP:世界気候研究計画、IGBP:地球圏―生物圏国際協同研究計画)などが声明を出して強調している。
また、2010年4月30日に開かれた日本学術会議主催シンポジウムでもこれらの結論を疑わせる議論は全く出なかった。
もとより、報告書内容の信頼性に関する問題が生じたことは遺憾であり、IPCC関係者はそのようなことが起こらないよう今後とも努力する必要があるが、これをもってIPCCの科学的知見全体の信頼性に疑いがあるとするのは不適切と言えよう。人為起源温室効果ガスの増加による気候変動は間違いなく進行しており、迅速に対応を進める必要がある。
3. 報告書の知見の政策決定への利用
本文で取り上げる第2のポイントは、IPCC報告が行っているのはあくまでも科学的知見の報告であり、何等かの政治的な主張を行うものではない点である。
最近、各種メディアや政府(政治家)を含め各方面で、IPCCが科学の要請として「地球の平均気温上昇を産業革命以前の自然のレベルにくらべ2℃以内に抑制すること」や、それに基づく特定のCO2削減目標を推奨しており、政策はそれに従うべきであるとするような説明が行われているが、これは全くの誤解である。
IPCCの第4次報告書では温度上昇影響に関わる記述がいくつかある。例をあげるなら、第二作業部会報告書の技術要約には次のような記述がある。
1)「工業化以前の水準を2〜3℃超える地球温暖化とこれに伴う大気中CO2濃度の増加によって、生態系の構造と機能に相当な変化が起きる可能性が非常に高い」(英文原典「Climate Change 2007 Impacts, Adaptation andVulnerability」p. 38、日本語版「IPCC地球温暖化第四次レポート 気候変動2007」p. 150)、
2)「世界平均気温が1990年〜2000年水準より2〜4℃上回る変化は、主要な影響の数をあらゆる規模で増加させることになるだろう。例えば、生物多様性の広範な喪失、地球規模での農業生産性の低下、グリーンランドと西南極の氷床の広範な後退の確実性などが挙げられる。」(英文原典p. 73、日本語版p.185)
ただ、記述はこのような温度上昇の影響の可能性を記すにとどまっており、気温上昇を工業化以前に比して2℃以下に抑制するべき、という要請や推奨は一切行われていない。
そもそも、IPCCの報告書は、「政策決定に役立つもの(policy relevant)」ではあっても「特定の政策を推奨するもの(policy prescriptive)」ではない、との原則のもとに編纂されているものである。
IPCCは、発足以来一貫して自己の作業を科学的知見の要約とする考え方をとっており、特定の対応策に関する意見を推奨したことはない。この点は本年8月に開催されたIPCCの統合報告書の構成に関する会議でも改めて確認されたところである。
本来、温室効果ガス削減戦略や目標は科学のみから自動的に導き出されるものではない。科学に基づく気候変動のリスク評価、対策のオプションやその費用の評価、種々の社会経済的変化の可能性、社会的価値の判断などを含めた幅広い見地から総合的に判断を行うべきであり、温度上昇の影響のみが判断の基準ではない。温暖化の政策は上記の諸因子についての総合的判断から導き出すべきものである。
その意味で、現在G8の宣言などで述べられている2℃抑制とそのための削減案(たとえば2050年世界の温室効果ガス排出50%減)は、あくまでもIPCCの科学的知見を参考とした先進国主唱の政治的判断の一つである、とみるべきである。決して科学的要請というべきものではない。
各国の対策に関する主張は、IPCCの知見は参考にしつつも上記のような諸要素を考慮にいれて定めるべきであり、世界はこの各国の主張に基づいて国際的な合意を形成し共通の目標を設定するのが適切ではないか。
以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「科学/IPCCの要請により、○℃、××ppm」という言い方は間違いである、IPCCはあくまで科学的知見を要約する役目であって、何℃にすべきとか、何ppmにすべきとか、どういう対応策をとるべきとは言っていない、ということです。
「本来、温室効果ガス削減戦略や目標は科学のみから自動的に導き出されるものではない」という点をどう考えたらよいのか、そして、よく聞く「2℃以内に抑えなくては」というのはどういう背景なのか、どういう意味を持っているのか、次号で、上記の意見書にも参加している国立環境研究所の江守正多さんのコラムからご紹介します〜。