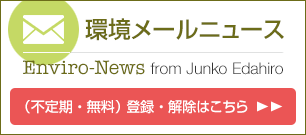エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
『Feed-in Tariffs』より日本の再生可能エネルギーの現状について(2008.08.19)
日本の中にいると、日本の現状や世界の中での位置づけなどがわかりにくいことがあります。
そんなとき、海外の人々や組織が日本の現状をどう見ているのか、世界の中でどのように位置づけているのかを見聞きすることが、一つの役に立つことがよくあります。(すべてを受け入れる、ということではなく、ある見方を教えてもらうことで、自分で考える糧を増やす、ということです)
そういう観点で、日本の現状を概覧するうえで役に立ったある本の一部を訳してお届けします。この本は、昨年レスター・ブラウン氏のところで、「世界で実際に変化を創り出しているしくみや事例を教えて」と聞いたときに、レスターが自分の書棚から引き出して貸してくれた本です。
ドイツなどでの太陽光発電の大きな普及を促進しているしくみである「固定価格買取制度」についての本でした。
Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy (2007)
Miguel Mendonca
この本に、各国の現状や見通し、課題などについて書いた章があるのですが、そこで日本がどのように取り上げられているか、興味津々で読みました。たまたま、そのあと、著者に直接会う機会があったため、「日本の部分、翻訳して伝えてよいかな?」と聞いたら、「どうぞどうぞ!」とのことでしたので、お伝えします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
7.日本
日本の太陽光発電技術は世界でもトップクラスに入る。もっともこれには、計画的な要素と偶然の要素が同じくらいあると言えそうだ。日本は、太陽光発電の設備能力ではドイツに次いで世界第2位であるが、化石燃料の輸入では世界のトップに位置し、そして少なくとも政府レベルでは、原子力エネルギーを積極的に推進している。
日本は、国土が狭くて国内のエネルギー供給が乏しく、多くの人口密集地域を抱え、おまけに海を挟んだ向こうには、エネルギーを渇望する隣国、中国が控えている。他国と同様日本にも、自国のエネルギーの将来に不安を抱く根拠はあるのだ。
現在、日本の電力供給量のおよそ3分の1を占めるのは原子力発電――地震国にとっては極めて問題の多い選択肢――である。だが、広島、長崎の出来事と、今なお相次ぐ安全性の問題や不祥事が相まって、国民の間には原子力技術への不信感が生まれている。しかし日本は、交渉の議長国として、排出量削減に関する初の条約である「京都議定書」をまとめ、その結果、クリーン・エネルギーの必要性に対する人々の認識が大いに高まった国でもある。
この国のこれまでのエネルギー政策のあり方や、独占的な電力会社のもつ圧倒的な影響力はさておき、日本のエネルギー・ミックスの将来に、再生可能エネルギー源がますます大きな役割を果たすことになると信じる根拠はある。日本は自国の排出量削減目標を達成できない可能性が高い――この事実が、本腰を入れた取り組みを促すことになるかもしれない。
とりわけ太陽光発電技術において、非常に広範かつ確立した研究・開発や生産基盤をもつことや、世界のウラン埋蔵量が減少していることから、日本が再生可能エネルギー源の利用を加速させるのは時間の問題だと示唆する楽観的な見方もあるだろう。だがこれまで、再生可能エネルギー源の開発は国内のエネルギー政策によって阻まれ、2010年の再生可能エネルギー源の利用目標は、エネルギー供給量全体のわずか3%と驚くほど消極的なものである。
日本が初めて再生可能エネルギーの研究・開発プログラムに着手したのは1974年。その後の30年間で、国内の設備能力は1GWの水準を超えた。これは、補助金制度やネット・メータリング制度(再生可能エネルギーによる余剰電力を電力会社が買い取るしくみ)によって、数十万もの住宅や企業、公共施設への太陽電池パネルの設置が進み、またこの間の製造コストが半減したことによるものだ。現在、日本の太陽光発電システムの生産量は世界全体の4割を超え、同産業は、世界のトップ企業が名を連ねる中、何年にもわたり年率30%の成長を遂げた。
自主的なネット・メータリング制度は、日本の太陽光発電の発展に貢献する中心的な要素の一つである。大手電力会社10社は1992年、太陽光発電と風力発電からの余剰電力を通常の電力小売価格と同額で買い取る独自のしくみを発表した。
夜間は1キロワット時当たり7円、日中は1キロワット時当たり30円という特別な価格が支払われる。ネット・メータリングのしくみは政府の施策ではなかったものの、これにより市場は大幅に拡大した。またこれは、再生可能エネルギー支援に向けて独自の条件を設定することで、政府のいかなる規制も回避しようという電力会社の動きとさえ考えられるかもしれない。
太陽光発電のサプライ・チェーンにおけるさまざまな要素を活性化させるために一連の政策が導入され、これによって価格が低下、従来のエネルギーに対して競争力をもてるようになった。「補助金の対象となっている従来のエネルギーと競合するためには、市場創設の早い段階での支援が必要である」ということがあらためて明確に示されたのだ。
残念なことに日本では、再生可能エネルギー源の前にはたいていさまざまな壁が立ちはだかっている。多くの場合その壁は、市場を独占している電力会社であり、政府自身だ。
電力会社は、しばしば安定性の問題を理由にして風力の導入も阻止しようとしてきた。また、地熱は、このような火山国にとっては将来性の見込めるエネルギー源であるが、地熱のある場所は保護されている国立公園の中にある場合が多く、しかも電力会社の抵抗が強まって開発が妨げられたばかりか、温泉ビジネスとも競合している。
1998年には、風力発電の商業化に向けて「自主的なネット・メータリング」制度の改訂版が導入された。買い取り価格は1キロワット時当たり15円と良かったものの、契約期間は1年に制限された。電力会社は価格の上昇を避けようと、買い取り価格を下げる代わりに契約期間の延長を申し出た。
風力発電にとってこれは、偶然にも幸運な出来事となった。契約期間の延長によって投資リスクが軽減し、開発に拍車がかかったのだ。ところが、1998年4月に北海道電力(HEPCO)がこの制度を公表した際の風力発電導入枠は、わずかに3MW。これに対してHEPCOには、1998年末までに500MWをも超える風力発電開発の応募があった。この結果を受け、HEPCOは1999年4月、やはりこの時も安定性の欠如を導入制限の理由として挙げ、風力発電の導入枠を150MWに制限したのだ。このような形で他の電力会社もこれに追随していった。
日本の太陽光発電市場は、同産業の成長の原動力となる、送電網に接続するシステムの設置を柱としてきた。住宅用太陽光発電市場は、経済産業省による「住宅用太陽光発電導入促進事業」の支援を受け、これが功を奏して10年間にわたり大きな成果を上げ、2003年度1年間の設備能力は200MW強に達した。
一般家庭への設置に初めて補助金が適用されたのは1994年。当初は、設置にかかる追加的費用の50%が補助金で賄われたが、1997年には設備能力1キロワット当たりの固定価格に変更され、この年の設置件数は5,654件となった。その後、補助金は、1997年の1キロワット当たり34万円の水準から同9万円へと徐々に減額されていった。
ネット・メータリング制度にこうした支援策が加わり、太陽光発電システムはますます魅力的なものとなった。2003年の1年間だけで、日本で設置された住宅用太陽光発電システムは5万3,000件近くに達し、2004年3月までに、「住宅用太陽光発電導入促進事業」から一部助成を受けて設置された太陽光発電システムは16万9,000件となり、およそ623MWの電力が供給された。また、補助金の提供は地方自治体も行っている。(Jones, 2005)
2003年には、262の地方自治体が太陽光発電に対して経済的援助を実施している。経済産業省による補助金制度は2005年までに段階的に廃止されていった。補助金の価格がかなり低くなっていたため、再生可能エネルギーの促進にほとんど貢献しなくなっていたのだ。それでも電力業界は補助金の撤廃に不満を抱き、これを理由に、自主的に行っていた独自のネット・メータリング制度の廃止を検討した。
また2003年には、2つの主要な法律が導入された。一つは、発電、電気工事、安全点検を規定する「電気事業法」の改正で、新規参入事業者が、拡大する対象顧客に対して電力の販売を行えるようになった。
対象となる顧客は、2004年度(2004年4月〜2005年3月)に、契約電力500キロワット以上の中規模企業に拡大したのを皮切りに、2005年度には契約電力50キロワット以上の小規模企業まで広がった。
これにより、発電能力の比較的低い独立系発電事業者が電力小売事業に参入することが容易になった――この分野においては大きな転換である。この法改正を受けて、20を超えるエネルギー供給事業者が設立された。だが依然として市場の99%以上を独占しているのは、既存の電力会社である。従って、こうした業界の現状下では、この法改正は今のところ再生可能エネルギーを大幅に促進する力にはなっていない。
もう一つ、法制面での大きな進展は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の導入である。これは割り当て制で、RPS制度(Renewables Portfolio Standard)とも呼ばれている(第6章参照)。
これにより、大手電気事業者は、「新エネルギー」を発電するか、もしくは「新エネルギー」から得られる再生可能な電気を購入することが義務づけられる。この法律で「新エネルギー」の対象となっているのは、風力、太陽光、地熱、バイオマス、水力である。電力買取法の導入に向けた取り組みもなされたが、ここでは割り当て制が採用された。
地球温暖化の影響への対応は、日本の現在の環境政策の柱となる目標の一つである。にもかかわらず、掲げられている目標は、経済産業省による「2010年までに原油換算でおよそ1,640万トン相当の新エネルギーを導入する」というものだけである。これは、2010年までに電力会社の電力供給量全体に占める再生可能エネルギーの割合を1.35%にするという目標を設定しているに過ぎない。これは目標というより、制約を拡大するという結果につながっている。
日本の太陽光発電システムの価格はこの数年で劇的に下がり、住宅用太陽光発電システムの価格は、10年も経たないうちに3分の2近く下がった。同様に、産業・公共施設用システムの設置価格も低下し、2001年に初めて1ワット当たり1,000円を切ると、2年後には800円にまで下がった。
産業・公共施設用システムの設置は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によるフィールドテスト事業のもとで推進され、これが価格低下の実現を後押しした。NEDOは経済産業省によって設立された組織で、中・大規模システム導入の効果を実証するため、1992年にフィールドテスト事業を開始した。(Jones, 2005)
2005年に発表されたレポート『仮題:日本の太陽光発電市場2004‐2005年――現在の課題と将来の見通し、および日本の太陽光発電の取り組み』(PV market inJapan 2004-2005-Current Topics & Future Prospects, and PV Activities inJapan)は、日本のエネルギー総合戦略における太陽光発電の重要性を強調している。
政府は、気候やエネルギー問題に対する国民の意識を高め、太陽光発電が、地球にとっても国民一人ひとりにとっても利益をもたらす可能性があることを明らかにするために努力を重ねてきた。これを後押しすべく、政府も地方自治体もさまざまなメディアを用いて、より広範な環境問題の観点から見た太陽光発電のメリットについて、国民に対し継続的な広報活動を展開している。
レポートでは、太陽光発電システムの増加を支えているのは、「たとえ経済性が『低いまま』であっても、自分たちが太陽光発電システムを購入することによって影響が広がる」ことを十分に認識している消費者であると結論づけている。
また、「太陽光発電システム市場は、特に一般住宅、公共施設、産業・企業用施設向けを中心に拡大し、システムの研究・開発・利用に対する政府の助成によってコスト削減を達成して、近い将来、持続可能な市場になることが期待される」と述べている。
さらに、このレポートの2030年に向けた「太陽光発電システムのロードマップ」の概要の中では、「2030年までの期間は、太陽光発電システムの本格的な市場創設における極めて重要な育成段階になるだろう」と指摘している。
日本の太陽光発電は、2030年までに累積設備能力100GWを達成できると考えられており、そうなれば一般家庭の電力需要の50%、すなわち日本の電力供給量全体の10%を太陽光発電で賄うことができる。また、発電コストは、研究・開発により2010年までに1キロワット時当たり23円、2020年までに14円、2030年までに7円を達成目標としている。(Jones, 2005)
京都議定書
1997年に開催された気候変動に関する京都会議の議長国である日本は、京都議定書を一貫して最も強く支持している国の一つである。2002年6月にはこれを批准し、2012年までの炭素排出量の大幅削減――日本の場合は1990年レベル比で6%削減――に向けた積極的な姿勢を明確に打ち出している。
だが、日本の削減実績は驚くほど芳しくない――実際に炭素排出量はおよそ8%増加している。このペースでは、京都議定書で約束した義務を達成する見込みはほとんどなく、それどころか、今後10年間に最大の温室効果ガス(GHG)排出国の仲間入りをするであろう他のアジア諸国に対して、否定的なシグナルを送ることになる。
日本のエネルギー効率の高さには定評があるが、実はこれは家庭部門に限られた話だ。産業部門のエネルギー集約度はドイツと同程度である。家庭部門における効率性は依然としてかなり高く、環境エネルギー政策研究所(ISEP)によれば、国全体の排出量に占める家庭部門の割合は5%に過ぎないという。それでも、家にモノが溢れれば、結局は消費の拡大によって効率性の向上が相殺されてしまう。
日本の地理的・文化的な特性も、ある程度エネルギー効率化の原動力に影響を及ぼして、エネルギー効率分野で最先端の技術革新をもたらし、ひいてはこれが輸出市場における競争力にもつながった。
影響を及ぼした大きな要因としては、エネルギー小売価格の高さが挙げられる。これにより、製造業などのエネルギーを大量に消費する分野では、エネルギー利用の効率化が図られるようになったのだ。家電製品の効率性はどんどん良くなっているが、日本政府はさらに、家庭での電力消費量が最も多いエアコンのメーカーに対して、2010年までに消費電力を20%削減する製品設計を義務づける法律を策定した。また、鉄鋼、自動車、電機に至るまで、日本のメーカーは世界でもトップクラスのエネルギー効率を誇る。
すなわち、日本が排出量をさらに削減しようとすれば、米国や欧州連合(EU)の場合に比べると、炭素1トン当たりの削減コストがかなり高くつくということだ。日本はこれまでに世界で最も燃費の良い車を作り、車の燃費の悪さでは世界でもトップクラスの米国でかなりの数これを普及させてきた。日本のメーカーは、燃料電池やハイブリッド、代替燃料エンジンの開発において他の追随を許していない。
日本は、クリーン開発メカニズム(CDM)や共同実施をはじめとする京都議定書の各要素に大きな関心を示している。これらは、先進国企業が、京都議定書の数値目標を上回る国や、議定書の対象から外れている国からカーボン・クレジット(炭素排出枠)を購入したり、より簡単かつ低コストでさらなる効率化を達成できる国の炭素削減プロジェクトに投資したりすることで、クレジットを取得できるしくみである。
たとえば、東京都を拠点とする東京電力は、タイのキャッサバ加工プラントに投資し、その発電用植物から放出される強力な温室効果ガス(GHG)であるメタンガスの燃焼炉の導入を進めている。2002年以降、日本政府が承認したCDMプロジェクトは40件を超えた。現在は、このような炭素取引の会計処理が適切に行われるように法整備が進められており、また、オランダの企業が、カーボン・クレジットを売買できる日本初の「炭素取引市場」の構築を検討している。(Head,2006)
これまでさまざまな施策が実施されてきたが、残念ながら、日本が京都議定書の数値目標を達成できない確率は高いように思われる。今後はこうした事態への対応策として、炭素税や排出量上限枠の設定、固定価格買取制度(FIT)を真剣に検討する必要がある。
これを書いている時点で、京都議定書に代わる協定が次々と提案されたり、策定されたりしている。京都議定書の失敗は本書で扱う内容ではないが、それでも、議定書が排出量削減の成功を化石燃料の燃焼を抑えることに依存しているという点で、本書のテーマと大いに関係している。
日本は、いくらか偶然の要素はあるものの、国内での太陽光発電の利用において成功を収めてきた。だが、再生可能エネルギーの増産や同エネルギー技術の輸出を進め、投資環境の改善を促すには、現行の割り当て制よりも優れた施策を検討すべきである。
東京都では買取制度のモデルが提案されており、こうした検討に着手する自治体第一号になるかもしれない。エネルギー分野の自由化は、競争力を後押しし、新規参入事業者に門戸を開くことになるだろう。だが、技術の領域を問わず、国の再生可能エネルギー源の潜在力への探求が本当の意味で加速するのは、国レベルの固定価格買取制度のもと、政府、民間投資家、そして日本国民の確固たる取り組み姿勢がうまく調和したときだと言えるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
太陽光発電については、日本も、6月9日に発表された福田ビジョンで、
> 特に、最近まで日本のお家芸であった太陽光発電の普及率で、現在ドイツの後塵
> を拝していますが、太陽光発電世界一の座を奪還するため、導入量を2020年まで
> に現状の10倍、2030年には40倍に引き上げることを目標として掲げたいと思いま
> す。
大きな目標を掲げました。目標があっても、実現するための「しくみ」がなくては、進みません。実効性のあるしくみが切に待たれています。