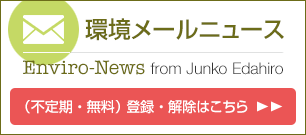エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
セカンドハンド新田恭子さんのお話:前編(2007.05.27)
先日、高松へ出張した折、前からお会いしたいと思っていたセカンドハンドの新田恭子さんとお話をすることができました。
セカンドハンドの活動はこちら。
新田さんの活動を知ったのは、環境を考える経済人の会21(B-LIFE)の朝食会での講演録を読んだことがきっかけでした。B-LIFEの2005年度第11回京都大学地球環境特別公開講座でお話しになった内容を、B-LIFE事務局の快諾を得て、ご紹介しますね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
新田恭子氏(NPOセカンドハンド代表)
松下和夫 今日は今年最初の講座ですが、来週で最終回になります。
今日は、NPOセカンドハンド代表の新田恭子さんをお招きしています。全体で12回の講座があったのですが、唯一の女性講師ということです。残念ながらこれは日本の現状を反映してしまったのかもしれません。そのようなことで是非期待をしてお話を伺いたいと思います。
新田さんは、大学を出られた後、ディスコのDJから始まって、フリーアナウンサーになられて、海外に旅行をしている中でいろいろな出会いがあり、その経験をもとにしてラジオ番組などを担当するとともに、イギリスでチャリティショップという仕組みを知り、カンボジアに行ったことをきっかけとして、1994年にセカンドハンドというNPOを設立されて、現在香川県を中心として県内外で活動をされています。今日はNGOの立場から国際協力をされている新田さんからお話を伺いたいと思います。それではよろしくお願い致します。
平均就学年数が4.6年程度のカンボジア
新田恭子 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、セカンドハンド代表の新田と申します。
本業がフリーアナウンサーということで、日頃からこのようにマイクを持って会場の隅でご挨拶をされる方のご紹介をしたり、ご結婚披露宴などで、司会をするのが私の本業です。そのかたわらでセカンドハンドというNPOを12年前に立ち上げて活動しています。
今日は、なぜ私がこのような活動を始めようと思ったのか。どのようなことがきっかけになって、どのようにこの活動を始めたのか。また、カンボジアの現状などをお話させていただければと思います。
その前に、世界の状況、今の世界の貧困問題について触れたいと思います。現在、世界には約190ヵ国、63億人の方がいらっしゃいますが、貧困の原因の問題を抱える国が130を超えます。世界63億人の、約4分の3の約43億人は開発途上国で暮らす人です。
約20%、地球上の5人に1人が1日1ドル以下の収入、12億人が極度の貧困に苦しむ人と言われています。途上国では1日1ドル以下の収入ですが、日本はというと1万ドルで約1万1,000円、100倍になります。
世界中で2億4,600万人の子供が働いています。5歳から14歳の子供が働かざるを得ない状況で働いているのですが、この2億4,600万人という数は、アメリカの人口とほぼ同数、日本の人口の約2倍という数です。
また、世界の17%の人々が安全な水を飲めません。初等教育の就学率は、今上昇していますが、就学しても卒業できる子供が半数程度という状況です。いまだに就学年齢に達しているのに、1億3,000万人の子供が学校に通えない状況があると言われています。その内97%が途上国に暮らす子供たちです。
そして、毎日、世界各地で3万人を超える子供たちが予防可能な疾病で死亡しています。エイズ(HIV)の問題も深刻化していますが、2004年新規にHIVに感染した15歳未満の子供は、世界で64万人です。多くが母子感染で、その9割がアフリカ地域と言われています。世界で毎日1万4,000人が新たに感染しており、アジアでも猛威を振るい始めています。このエイズによる孤児も、現在1,500万人以上いると言われています。
このような世界の現状の話を聞いて、「関係ないな」と思っている人もいるかもしれません。しかし、これは全く関係ない話ではなく、皆さんとこの世界の人々はつながっているのです。貧困問題、国が経済的に貧しいということは、その国の何が原因してということではなく、それは地球上のいろいろなかたちでつながっています。
少なくとも、今日皆さんは私を介して、カンボジアという国とつながっています。今日は皆さんにそのカンボジアの話もさせていただきたいと思います。
カンボジアは、平均就学年数が4.6年程度だと思います。小学校に入学をしても、辞めなければいけない子供たちが非常に多くいます。特に、女の子達は卒業までなかなか学校に通うことが出来ません。
カンボジアの乳幼児死亡率は14%。たくさんの子供たちが出産の時や感染症などが原因で命を落としています。このカンボジアの現状を少しでも良くしたいということで、私どもは教育、自立支援、そして個人への支援などを行っています。
今日は、中盤でその活動の紹介をしているビデオを皆さんにご覧いただきたいと思っていますので、カンボジアの様子もそこを通してご覧いただけるのではないかと思います。
リユースで国際協力を行うセカンドハンド
セカンドハンドの仕組みですが、今日のタイトルが「チャリティショップ(リサイクルショップ)と国際協力」だったのではないかと思いますが、正確に言うと「リサイクル」ではなく、「リユ-ス」と言ったほうがいいと思います。リユースで国際協力を行っています。ただ、日本ではリサイクルショップが定着しているので、私どもは「リサイクル」と呼ばせていただいておりますが、私どもはこのリユース活動でチャリティショップをやっています。
この仕組みですが、全国の皆さんから不用になったもの、もしくは皆さんがどなたかにいただいたけれども使わないもの、タンスの肥やしになっているものなどを無料で提供していただきます。そして、その仕分け、値付け、またお店で販売するのですが、お店に立って販売をする販売員、こういった方々はみんな無報酬のボランティアの方々です。そして、そのお店、物を管理する倉庫は、無料、もしくは格安でお借りしている物件です。そして、企業がいろいろなかたちで協力をしてくれています。
このセカンドハンドは、そもそもイギリスのチャリティショップを見かけたことがきっかけでスタートすることになりました。イギリスにはチャリティショップが3,000店舗以上あります。町を歩けばいたるところにこのようなチャリティショップがあるので、イギリスに行かれた方、特にロンドンに行かれた方は、いろいろな団体がやっているチャリティショップを覗かれたのではないかと思います。
国際協力をしている団体もあれば、ある団体は動物愛護のため、ある団体は自然保護のため、また老人福祉のためであるとか、障害者のためであるとか、いろいろな目的を持ってチャリティショップを運営しています。ですから、商品を提供したいという人も、どの活動を支援したいかによって持っていく先を決めればいいのです。
また、お買い物をすることも出来る。市価よりもずいぶん安く買えます。最近リサイクルショップも、日本ではかなり普及しているので、そういったところを利用されている方も多いと思いますが、そのような商業ベースに乗るのではなく、買うことが寄付につながるというシステムです。
商品をゴミにするのではなく、まず誰かに生かしてもらう(リユース)という意味で、これは環境に大変良いのではないかということと、この売上が誰かの懐に入るのではなく、それがチャリティショップを介して困っている人のために役立てられる。また、世界のために役立てられるというものです。私は、このシステムをイギリスで見て大変感銘を受けました。
滅私奉公ではなく、自分が笑顔になるのがボランティア
最初はイギリスのチャリティショップで、知らずにお買い物をしていたのですが、友人が私の買い物をした袋を見て、「チャリティショップでお買い物をしたのね」と言ったので、「チャリティショップって何?どんなお店?」と聞いたところ、みんなが無料で持ち寄ってきて、無償で働く人たちが販売をして、その売上で困っている人たちのためにいろいろと役に立つ活動をしているという話を聞いて、目から鱗という感じでした。
そのようなことが成立するのかと疑問に思いました。そもそもみんなが無料で物を持ってくるのだろうか。ただで働くのだろうか。中古のものを買うのか。今から15年前にそのシステムを知ったのですが、当時はまだまだリサイクルというものが日本では一般的ではなく、中古の衣類を着るということに非常に多くの方が抵抗を持っていたと思います。ですから、そのようなお店が成り立つわけがないのではないかと思いました。しかし、合理的で非常に良いシステムだと思いました。もっと知りたくなった私は、改めてイギリスに行って、そのシステムをどのように運営しているのかということをマネージャーの方にお話を聞くことにしました。
私は、世界を旅することが非常に好きなので、これまで35ヵ国以上を、主に1人で旅をしています。よくロンドンを拠点に中東のほうに行ってみたり、ヨーロッパ地域を回ったりしていたので、ロンドンに行った時にはチャリティショップに寄っていたのですが、もっとチャリティショップ自体を知りたいと思い、2〜3週間程度滞在をして、いろいろな地区のチャリティショップを見て回りました。
どのお店も活発に活動していました。リバプールでもチャリティショップに入ったのですが、そこで店番をしていたおばあさんが、私が買ったものをきれいにたたみながら、「私はこうやって、こういうところに働けることが、役に立てることが本当に幸せなのよ」と言われました。
白髪で90歳を超えた方ではないかと思いますが、レジを打つ手も振るえて、値札も十分に見えないくらい目がかすんでいらっしゃる方なのですが、その震える手でレジを打ちながらそのように語ってくれました。「こうやって誰かの役に立てるのが本当にうれしいの」と言って「Thank you」と言った時の笑顔がキラキラとして見えました。
私はそれまでボランティアや国際協力というのは、興味はありましたが、ボランティアをやる人というのは何か特別な人なのではないか思っていました。募金はしても、団体の中で積極的に活動する気はありませんでした。ボランティアに対するイメージは、自分を殺して人様の役に立つという「滅私奉公」的なものでしたが、実際にそのおばあさんに出会って、自分が輝いてもいいのだということを感じさせられました。
そのおばあさんに会って、私のボランティアに対する概念がずいぶん変わったような気がします。それも一つの大きなきっかけだったのではないかと思います。私もこうやって「誰かの役に立つのがうれしい」とか、「誰かに喜んでもらえるのがうれしい」というような活動がしたい。日本にもないのかと思い、帰国していろいろと調べてみたのですが、日本にはこのようなチャリティショップは当時は一つもありませんでした。
遠い昔の話ではなく、今も心に影を落とすポル・ポト時代
イギリスに行った直後、カンボジアに行く機会を得ました。カンボジアも大変興味のある国ではありました。アンコールワットがあるので、是非行ってみたいと思っていたのですが、内戦がまだまだ続いている状態なので、1人で行くのはまだ怖い。そのような時に、ユネスコが主催する「青年ワークキャンプ」があり、現地の大学生たちと寝泊りを共にしながらボランティア活動ができる、楽しそうだ思い、飛びつきました。
行く前に、カンボジアについていろいろな本を読みました。そこで初めてポル・ポト時代が、自分が生まれた後の出来事だということを知りました。正直それまでニュースなどでは見ていましたが、ずいぶん昔のことだというイメージを自分の中で持っていたのですが、ポル・ポト時代は1975年から1979年です。
私は1965年生まれなので、当時10歳であった時にポル・ポト時代があったということを知り、非常にショックでした。ポル・ポト時代に同じ歳の人がどのように生き延びたのか。行く前にたくさんの書籍を読みました。ポル・ポトに関する情報や、「ポル・ポト政権がどのようなことをやったのか、なぜこのようなところに至ったのか」という分析をするような書籍はありましたが、「その時代に子供たちがどのように過ごしたのか」ということを書いている本がなかったので、私は同じ年の青年に話を聞きたいと思いました。
私は当時「地球村レポート」というラジオの番組をやっていました。自分で現地に行って取材をしてきて、編集して流すというものだったのですが、その「地球村レポート」という番組の中でカンボジアの青年の話を聞こうと思い、1994年2月にカンボジアに行く時に、録音の機材も持って現地に行きました。
ユネスコで働いていた青年が、私と同じ年だったので、その彼に話を聞くことにしました。親しくなったところで、話を聞かせてほしいと頼んだのですが、彼の答えは「ノー」でした。
非常に明るい人だったのですが、その話をした途端に下を向いて動かなくなってしまったのです。いかに彼にとって大きな事件だったのか。いまだに心の傷が残っていて、その傷がどれほど大きいのかがわかった気もするのですが、とにかく話を聞かないことには、何があったのか。どのように過ごしたのかということが、全く想像すら出来ない。多くの日本の人たちがそうだと思います。
ですから、「あなたの話を聞かせてほしい。私がそれを伝えることで、少しでも多くの人にカンボジアのポル・ポト時代にどのようなことがあったのかということを伝えることが出来るので、よければ話してもらえないか」と彼に頼みました。そうすると、2〜3日して彼のほうから「話してもいいよ」と言ってくれました。
人口900万人のうち200万〜300万人が虐殺
彼の話はこうでした。
1975年、彼のお父さんは政府の高官でしたが、ポル・ポト時代が始まってすぐに連れて行かれました。当時カンボジアの人口は約900万人と言われていますが、知識階級の方々がターゲットになって大量虐殺が繰り広げられ、200万〜300万人の人が殺されました。
彼のお父さんもその1人として連れて行かれて、そのまま帰ってくることはありませんでした。どこで、どのように殺され、どこにお父さんの骨が埋まっているのか、今もわからない。今度はお母さんが連れて行かれそうになりました。強制労働の現場に連行されるということでしたが、彼はまだ兄弟が幼いので、お母さんが連れて行かれると困ると思い、代わりに自分が行くと名乗り出たそうです。弟、妹にまだ乳飲み子の赤ちゃんもいたということです。彼は7人兄弟でした。
彼がお母さんの代わりにダムの建設現場に行きました。強制労働の現場には、家族ぐるみで強制移住させられて労働をさせられているところもあれば、家族と離れ離れになって送られている人もいました。ずっと監視をされている中で、何家族かが一緒になって一つ屋根の下で暮らしていたということですが、1日中兵士なり、ローカル・ピープルと言われている地元に住む農民から行動、言動、全てを監視されていました。
ポル・ポトに対する悪口などをこっそりでも言っていたら、その夜「来なさい」と呼ばれて、その人は帰ってくることはなかった。そのようなことを何度も見ているので、とにかく何も言わず、逆らわず、毎日仕事をこなしていました。
ある時、畑で仕事をしていたら、近所の15歳くらいのお兄さんを見かけました。まだ9歳だった彼は、近所のお兄さんを見て非常にうれしかったので仕事をするふりをしながら近づいて世間話をしました。「帰りたい。お母さんに会いたい」と言いました。そうすると、そのお兄さんも「自分も帰りたい」「じゃあ、抜け出そうか」ということになって、2人でポル・ポトの兵士たちが昼寝をしているすきを狙って、畑の中をまずは匍匐前進で逃げて、山の中の手のひら程度の幅しかない獣道を一歩も踏み外さないように必死で走って逃げたそうです。
もし一歩踏み外すと、どこに地雷が埋まっているかもわかりません。そして、必死で逃げて家にたどり着くことが出来たのですが、翌日にはまた兵士に捕まって連行されたそうです。後ろ手に縛られてどのくらい歩いたのか。かなり歩いたと思うのですが、近所のお兄さんが、彼の目の前で頭を打ち抜かれて殺されました。
自分が誘うようなかたちで一緒に逃げた近所のお兄さん、小さい頃から一緒に遊んでいたそのお兄さんが自分の目の前で殺されたのは、彼にとっては大きなショックでした。自分も殺されると思ったのですが、「お前はまだ小さいから許してやる。でも、こうなるんだ。覚えておけ」と言われたそうです。
ポル・ポト時代が終わって、彼は家族と再会出来ました。これは非常にまれな話です。家族同士、5年、10年探し合って、ようやく巡り会えたという家族を何家族も私は知っていますが、そのような中でポル・ポト時代が終わってすぐに家族に会えたということは、彼は非常にラッキーだったと思います。
ただ、その家族がたった3人だけになっていたのです。お母さんと妹が1人だけになっていた。7人兄弟がたった2人兄弟になってしまっていた。小さな赤ちゃんは、お母さんのオッパイが出なくて栄養失調になりました。
お母さんはその赤ちゃんの体をさすってあげることしか出来なくて、死んで行くのを見守ることしか出来なかった。下痢になっても、当時病院などもなかったので、弱っていくのをお母さんはただ体をさすることしか出来なかった。安全な水も与えることが出来ず、そうやって小さな子供たちは命を落としていったのです。
彼の話を聞きながら、もし自分がカンボジアに生まれていたらどうだろうと思いました。そして、本当に背筋がゾッとするくらい怖いと思いました。そして、憤りに近い疑問を感じました。なぜだろう。同じ人間なのに。目の前にいる彼が、同じ年の彼が、生まれたところが違うだけで、なぜそのような思いをしなければいけないのかと思いました。
そして、自分の置かれた環境、この日本の現状を振り返ってみて、またいろいろな国々を旅行して思ったのが、自戒も込めて言うと、日本というのは1人ひとりが非常にわがままに生きている国だということです。そのような現状から見ても、日本には出来ることが多くあるのに、このままではいけないのではないか。日本に住む自分にも出来るチャンスがたくさんあるのではないか。何かをやらなければいけないのではないか。何が出来るのだろうというところに至ったのです。
修復しても、入れる本がない大学の図書館
カンボジアにはユネスコの主催する「青年ワークキャンプ」で訪れたと申しましたが、その「ワークキャンプ」というのは、大学の図書室の修復作業を行うというものでした。大学の図書室の修復作業をやったものの、実は中に入れる本がないということが後でわかりました。
ポル・ポト時代に、本という本は全てカンボジア国内で焼かれてしまいました。学校が虐殺の現場になったり、お寺が虐殺の現場になったり、収容所になったりしていました。実際に私が滞在していた大学も、教室は収容所となって、そこで多くの人が殺されたそうです。
その大学の前の広場は、「キリングフィールド」と呼ばれています。「キリングフィールド」という映画がありますが、「キリングフィールド」は1ヵ所だけではなく、カンボジアのいたるところにあります。その大学の前の広場も、祠が一つ建っていて、「開けてごらん」と言われたので開けてみたのですが、中には頭蓋骨や骨が山盛りでした。
「今あなたの立っているその下にもたくさんの骨が埋まっているんだよ。まだ拾い上げられていない骨があるんだよ」ということを言われて、ゾクッとしたのですが、その大学の図書室に本がないということを知りました。
なおかつ、大学生から本を送ってほしいと頼まれたのです。「英語で書かれた本なら何でもいい、活字が読みたい」と言っていました。教科書も当時はありませんでした。もちろん、辞書もありません。
自分はというと、1人1冊どころか、数冊の辞書が机の上にあった記憶があります。英和辞典、和英辞典、漢和辞典といったように、何冊も積み上げていた記憶があるのですが、カンボジアでは大学に1冊もないのです。先生が教壇に書いているものが全てです。
そのようなことで、「私が使っていた本でよければ送ってあげる」という約束をしてカンボジアを後にしたのですが、カンボジアから帰る飛行機の中で、あの本も、この本もと思っているうちに、もっといろいろな本が送ってあげたくなりました。
例えば、地球儀や地図も見せてあげたい。宇宙に関する本、生物に関する本、たくさん写真が載っていれば英語が難しくてもわかるのではないかなどと思っているうちにリストが膨大になって、買わなければいけない。「お金がない、どうしよう。」
その時に、イギリスのチャリティショップのことを思い出しました。あのシステムをやればいい。そうすると、日本でも多くの人にチャリティショップのことを知ってもらえるかもしれない。日本にもこのようなチャリティショップがあちこちに出来ればいい。それを知ってもらうためにも、もし自分が始めたことで「簡単に出来るんだ」と思ってもらえればいいのではないかと思い、始めようと決めました。
1994年2月にカンボジアに行って、3月に戻ってきました。そして、4月から動き始めて、5月にチャリティショップをオープンしました。
< つ づ く >