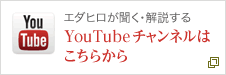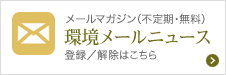つながりを読む
注目の幸せ研ニュース+対話力を身につけよう!

Photo by Beth Macdonald on Unsplash
https://unsplash.com/photos/group-of-people-sitting-on-green-grass-field-during-daytime-mbND4xtrlVY
このたび、幸せ研のニュース2024年4月1日~2025年3月31日の1年間のアクセス数トップ10のリストをつくってもらったので、共有します。
また読んでいないものがあればぜひ! どういうニュースに注目が集まっているかもぜひ感じてください。
1.地域ごとの男女格差が明らかに! 都道府県別ジェンダー・ギャップ指数
2.2024年上半期:激しい雷雨と洪水が自然災害による損害の主要因
3.Food Loss and Waste in Japan:
5.世界幸福度報告書:若者の幸福度が北米と西欧で下がっている
7.自治体を巻き込んだフードシェアリングサービスで、お店から出る食品ロスを削減 「タベスケ」の取り組み
8.家で食事を取る人の割合、コロナ禍の2020年と変わらず:東京ガス都市生活研究所調査
9.地域ごとの男女格差の詳細データを提供!都道府県ジェンダー・ギャップ指数l
10.ベーシックインカムはメンタルヘルスに良い効果をもたらす:米ミネアポリス市の試験的プロジェクトの中間報告l
アクセス解析の結果、幸せ研のサイトでは「対話」のテーマの読書会への関心が高いことがわかりました。
多様性が重要になってくる中、どう多様な人々と対話していくかのスキルや作法がないと、多様性は力にならず、逆に集団の思考や進捗の足を引っ張るものになってしまいかねません。
そういう問題意識で「対話力」につながるものを取り上げてきました。今月の読書会もそうです。ご興味のある方、ぜひ一緒に学び、考えてみませんか。
幸せ研読書会 6月18日(水)18:30~20:30
『対話をデザインする』
~~~~~~~~ここからご案内~~~~~~~~
6月の読書会では、細川英雄氏の書籍、『対話をデザインする――伝わるとはどういうことか』を、課題書に取り上げます。
「対話」は、ここ数年の私にとっても重要なテーマで、対話の枠組みや作法、トレーニングの仕方を整理して、作っていきたいと考えています。
先月の課題書『それでも、対話をはじめよう』とは、また違った視点で「対話」について考察している書籍で、「対話のデザイン」という側面から、みなさんと一緒に考えて、学びを深めていきたいと思っています。
「対話」について、学校では方法について教えてくれないけれど、家庭・仕事・地域・社会など様々な場面において、誰しもが対話をして日々を過ごしています。年齢問わず、人との対話において悩んだことが1度はあるのではないでしょうか。
話すとき、聞くときにどのようなことに気をつけたらいいのか? 伝わるようにはどのように工夫したらよいのか? など、対話をデザインする方法について、一緒に学びませんか。
https://www.ishes.org/news/2025/inws_id003644.html
~~~~~~~~ご案内ここまで~~~~~~~~
これまで、「対話」「共感」などのテーマでの読書会は以下のようなものがあります。いずれも音声受講もできますので、ご興味があるものがあったらぜひどうぞ!
『それでも、対話をはじめよう――対立する人たちと共に問題に取り組み、 未来をつくりだす方法』
https://www.ishes.org/news/2025/inws_id003634.html
『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』
https://www.ishes.org/news/2024/inws_id003590.html
『問うとはどういうことか』
https://www.ishes.org/news/2024/inws_id003504.html
『共感力』
https://www.ishes.org/news/2023/inws_id003469.html
さて、英語での東洋思想の授業準備に戻ります~。東洋思想のセミナーも、というお声もいただいているので、ぜひどこかで実現したいと思っています。混迷の時代だからこそ、自分の軸を作る上でもとても役に立つと思います!